Pythonで日付計算を行うとき、最初にぶつかるのが「datetimeとtimedeltaの違い」と、「何日後・何時間後をどう計算するか」という問題です。
本記事では、Python標準ライブラリのdatetime.timedeltaを使って、実務で頻出の「締切」「有効期限」「レポート期間」「シフト時間」などを正確に扱う方法を、図解とコード例付きで詳しく解説します。
Pythonのtimedeltaとは
datetimeとtimedeltaの基本関係
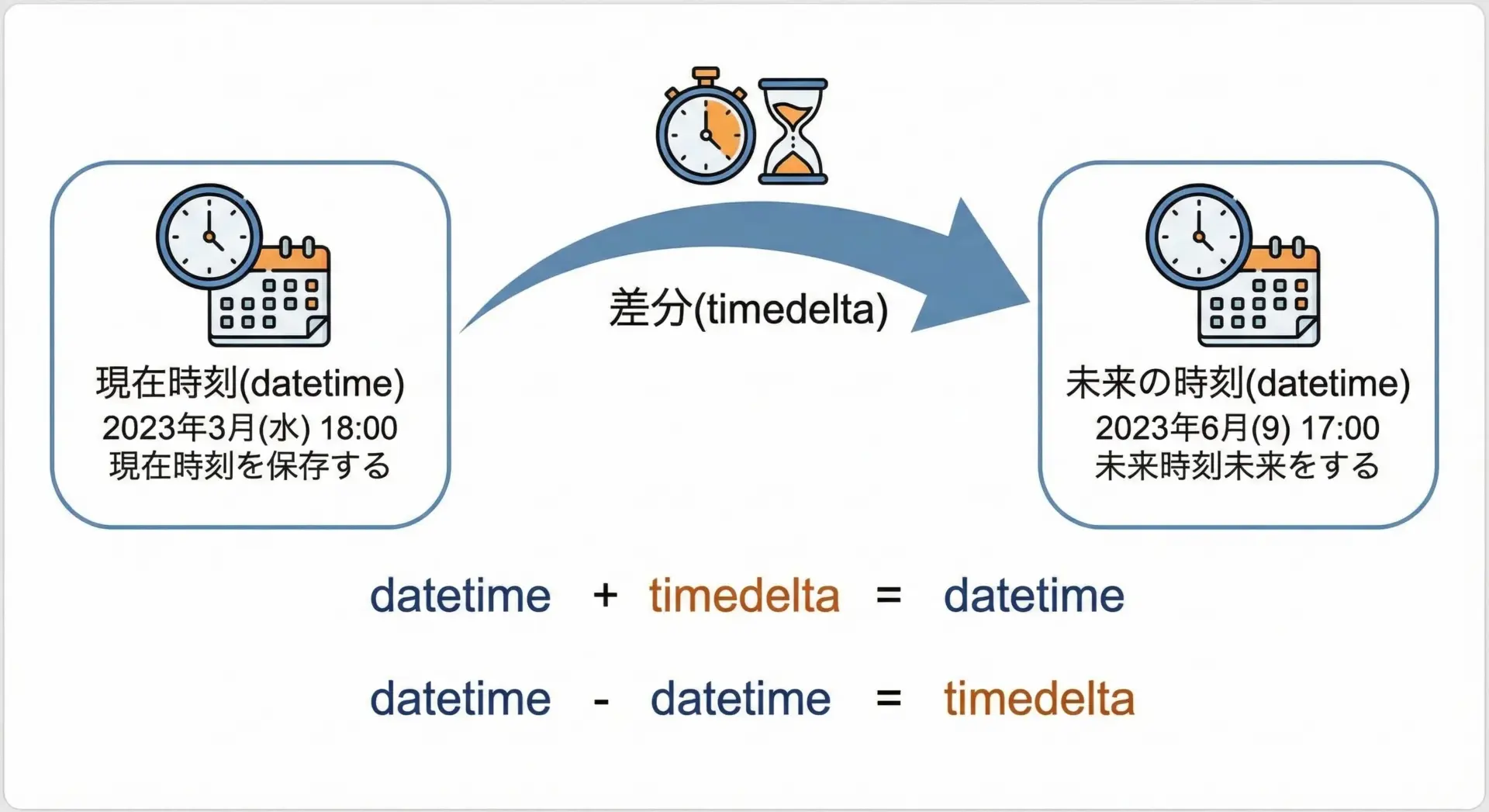
Pythonで日付や時刻を扱うときは、主にdatetimeモジュールを使います。
この中で「いつ」を表すのがdatetime.datetimeやdatetime.dateで、「どれくらいの長さ」を表すのがdatetime.timedeltaです。
datetimeは「点」、timedeltaは「長さ(期間)」だとイメージすると理解しやすくなります。
代表的な関係は次のようになります。
datetime + timedelta = datetime(何日後、何時間後を求める)datetime - timedelta = datetime(何日前、何時間前を求める)datetime - datetime = timedelta(2つの日時の差を求める)
具体的な型の関係を表にすると次のようになります。
| 式 | 結果の型 | 用途のイメージ |
|---|---|---|
dt1 - dt2 | timedelta | 2つの日時の差分(日数・時間)を知る |
dt + td | datetime | n日後・n時間後を計算 |
dt - td | datetime | n日前・n時間前を計算 |
ここで最も重要なのは、timedeltaは日付そのものではなく「期間」を表すオブジェクトだという点です。
datetimeとtimedeltaを軽く触ってみる
from datetime import datetime, timedelta
# 現在時刻を取得
now = datetime.now()
# 3日を表すtimedelta
three_days = timedelta(days=3)
# 3日後
three_days_later = now + three_days
# 3日前
three_days_before = now - three_days
print("現在:", now)
print("3日後:", three_days_later)
print("3日前:", three_days_before)
print("3日という期間の実体:", three_days)上記コードを実行すると、同じdatetimeからtimedeltaを使って「前」「後」の日時が得られることが確認できます。
timedeltaで扱える時間の単位

timedeltaは、次のような時間の単位を引数として指定できます。
dayssecondsmicrosecondsmillisecondsminuteshoursweeks
内部的には日・秒・マイクロ秒に正規化されますが、指定時には上記の便利な単位を使えます。
from datetime import timedelta
# 各種単位の指定例
td = timedelta(
weeks=1, # 1週間
days=2, # 2日
hours=3, # 3時間
minutes=30, # 30分
seconds=15, # 15秒
milliseconds=500, # 0.5秒
microseconds=250 # 0.00025秒
)
print("timedeltaの中身:", td)
print("日数(td.days):", td.days)
print("秒(td.seconds):", td.seconds)
print("マイクロ秒(td.microseconds):", td.microseconds)
print("合計秒数(td.total_seconds()):", td.total_seconds())timedeltaの中身: 9 days, 3:30:15.500250
日数(td.days): 9
秒(td.seconds): 12615
マイクロ秒(td.microseconds): 500250
合計秒数(td.total_seconds()): 797415.50025日・秒・マイクロ秒の3要素から、合計秒数はtotal_seconds()で取得できます。
後ほど差分計算で詳しく扱います。
timedeltaで日付・時間を加算する
日付に日数を足す(add)基本例
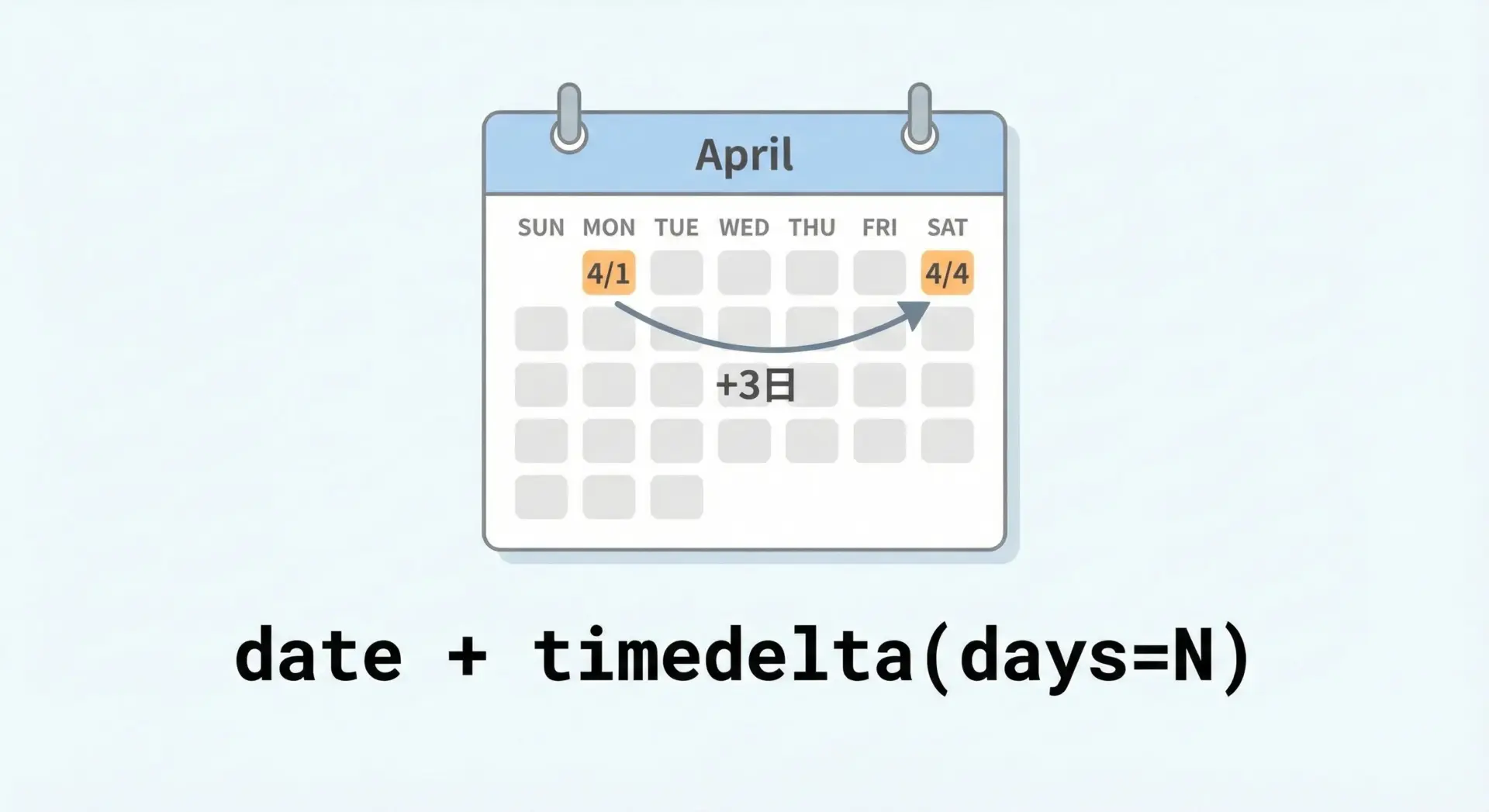
最も基本的な使い方は、特定の日付に日数を足して「N日後」を求める方法です。
from datetime import date, timedelta
start = date(2025, 4, 1) # 2025年4月1日
delta = timedelta(days=3) # 3日間
result = start + delta # 3日後
print("開始日:", start)
print("3日後:", result)開始日: 2025-04-01
3日後: 2025-04-04date型でもdatetime型でも、足し算・引き算の考え方は同じです。
from datetime import datetime, timedelta
start_dt = datetime(2025, 4, 1, 9, 0, 0) # 2025-04-01 09:00:00
one_day = timedelta(days=1)
print("開始日時:", start_dt)
print("1日後:", start_dt + one_day)
print("1日前:", start_dt - one_day)営業日や締め日計算にtimedeltaを使う
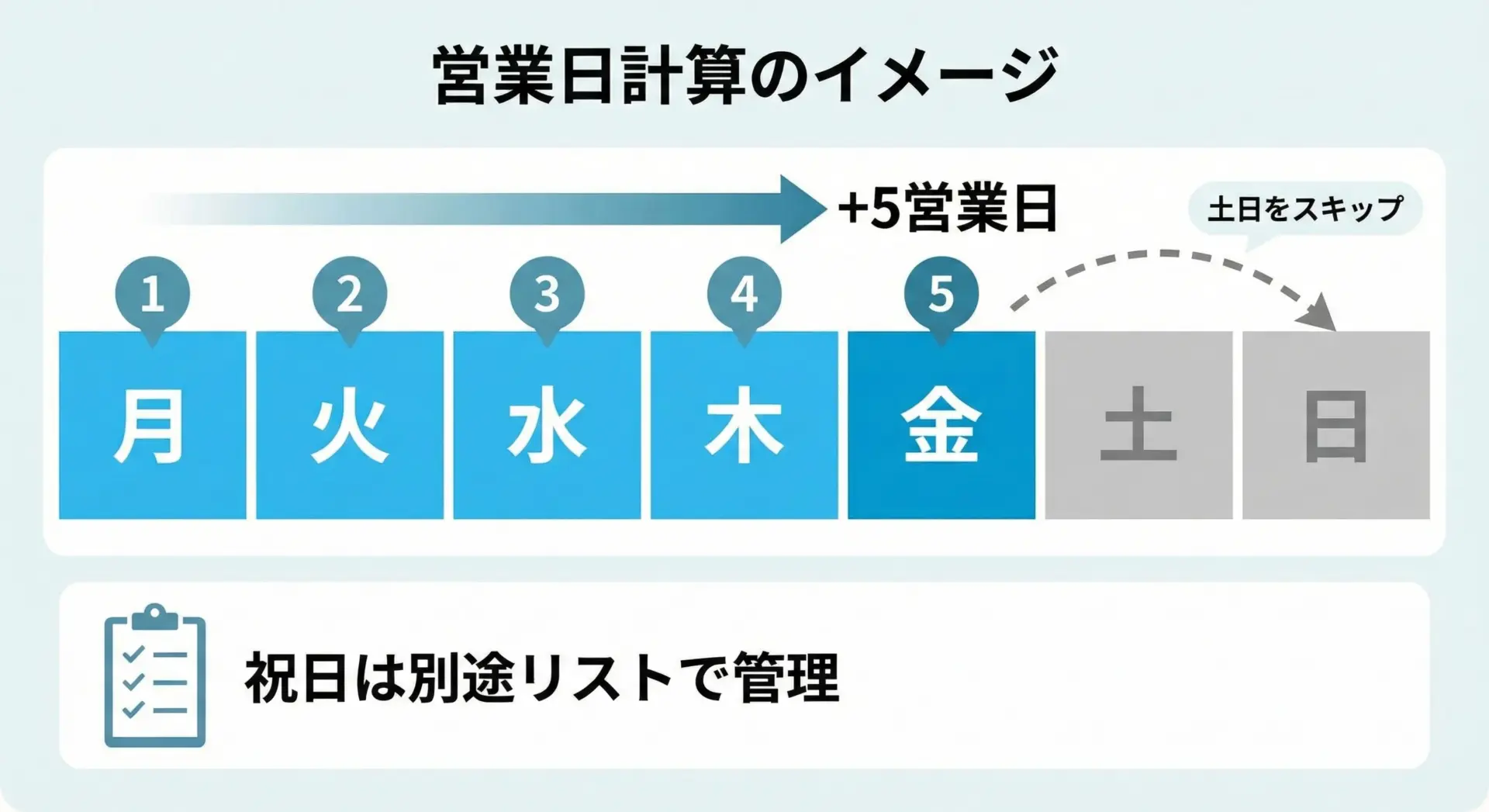
実務では、単純な「7日後」ではなく「5営業日後」「毎月末締め」のような計算が頻出します。
ここでは、土日を除いて営業日を数える簡易的な例を示します。
from datetime import date, timedelta
def add_business_days(start_date: date, days: int) -> date:
"""土日を除いて指定営業日数を加算する簡易関数"""
current = start_date
added_days = 0
while added_days < days:
current += timedelta(days=1)
# 月曜日=0, ..., 日曜日=6
if current.weekday() < 5: # 0〜4が平日
added_days += 1
return current
start = date(2025, 4, 1) # 火曜日と仮定
target = add_business_days(start, 5)
print("開始日:", start)
print("5営業日後:", target)開始日: 2025-04-01
5営業日後: 2025-04-08ここでは土日だけを除外していますが、祝日を考慮する場合は別途「祝日リスト」を用意し、それに含まれる日もスキップするように拡張します。
from datetime import date, timedelta
JAPAN_HOLIDAYS_2025 = {
date(2025, 1, 1), # 元日 (例)
date(2025, 1, 13), # 成人の日 (例)
# ... 必要に応じて追加
}
def add_business_days_with_holidays(start_date: date, days: int) -> date:
current = start_date
added_days = 0
while added_days < days:
current += timedelta(days=1)
is_weekend = current.weekday() >= 5
is_holiday = current in JAPAN_HOLIDAYS_2025
if not is_weekend and not is_holiday:
added_days += 1
return current締め日計算では、例えば「末日から3営業日前」を求めることもよくあります。
from datetime import date, timedelta
import calendar
def last_day_of_month(year: int, month: int) -> date:
"""月末日を返す"""
last = calendar.monthrange(year, month)[1]
return date(year, month, last)
def last_3_business_days_before_month_end(year: int, month: int) -> date:
month_end = last_day_of_month(year, month)
# ここでは土日だけ除外する簡易版
current = month_end
counted = 0
while counted < 3:
if current.weekday() < 5: # 平日
counted += 1
if counted == 3:
break
current -= timedelta(days=1)
return current
print("2025年4月の月末日:", last_day_of_month(2025, 4))
print("月末から3営業日前:", last_3_business_days_before_month_end(2025, 4))2025年4月の月末日: 2025-04-30
月末から3営業日前: 2025-04-25このようにtimedeltaを1日ずつ加算・減算しながら条件でスキップしていくことで、柔軟な締め日計算が可能になります。
時間単位(時・分・秒)の加算でシフト時間を計算
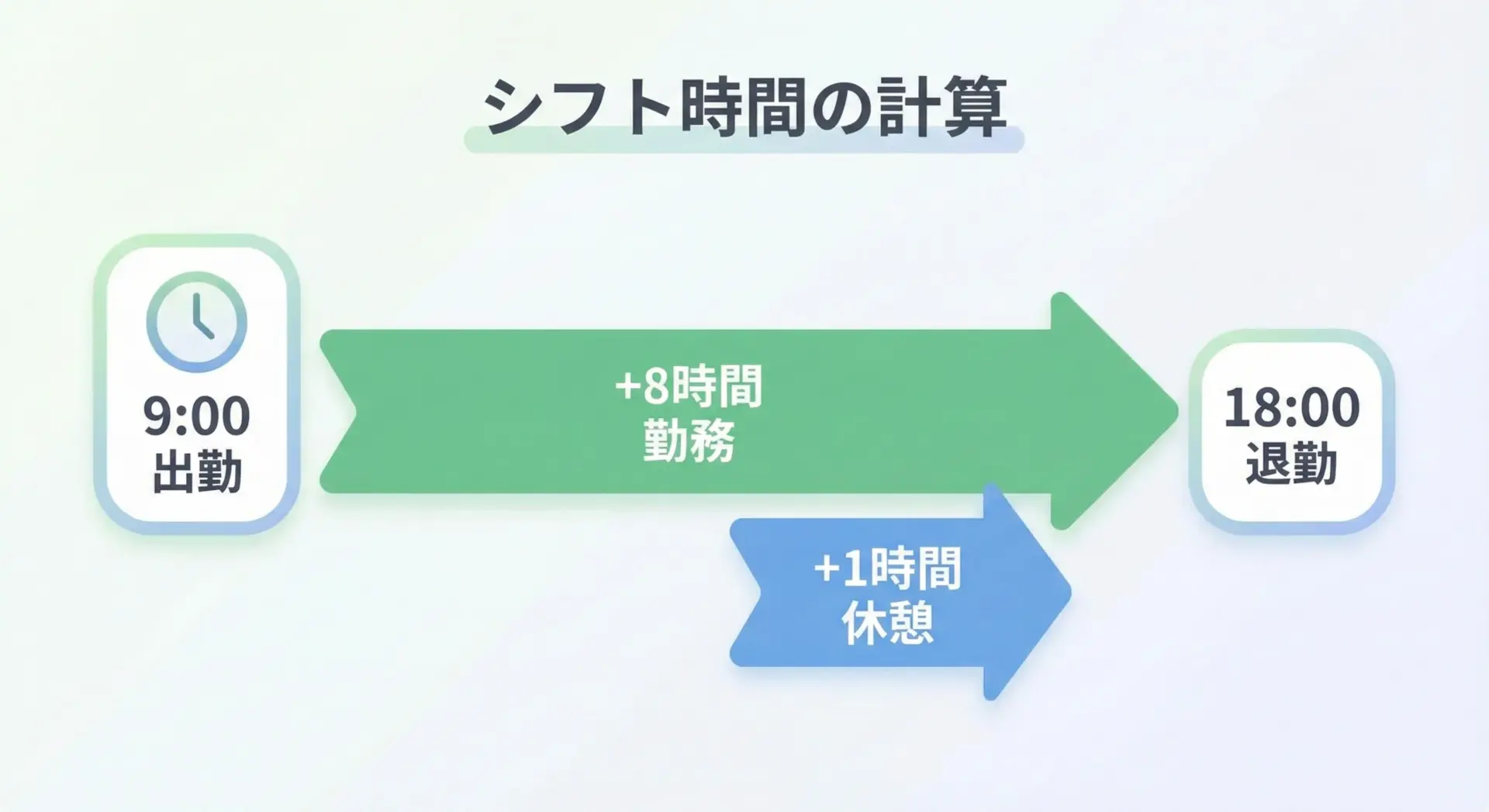
日付だけでなく、時刻ベースのシフトや稼働時間計算にもtimedeltaは有効です。
from datetime import datetime, timedelta
# 2025-04-01 9:00 出勤
clock_in = datetime(2025, 4, 1, 9, 0, 0)
# 実働8時間 + 休憩1時間 のシフト
work_hours = timedelta(hours=8)
break_time = timedelta(hours=1)
# 退勤時間 = 出勤 + 実働 + 休憩
clock_out = clock_in + work_hours + break_time
print("出勤:", clock_in)
print("退勤(8h勤務+1h休憩):", clock_out)出勤: 2025-04-01 09:00:00
退勤(8h勤務+1h休憩): 2025-04-01 18:00:00分単位でシフトパターンを扱うこともよくあります。
from datetime import datetime, timedelta
clock_in = datetime(2025, 4, 1, 22, 30) # 22:30出勤
shift_length = timedelta(hours=7, minutes=45) # 7時間45分
clock_out = clock_in + shift_length
print("出勤:", clock_in)
print("退勤:", clock_out)出勤: 2025-04-01 22:30:00
退勤: 2025-04-02 06:15:00日をまたぐ夜勤シフトでも、単純にtimedeltaを足すだけで翌日に繰り上がるため、複雑なロジックを書かずに済みます。
timedeltaで差分を求める
2つのdatetimeからtimedeltaを取得する方法
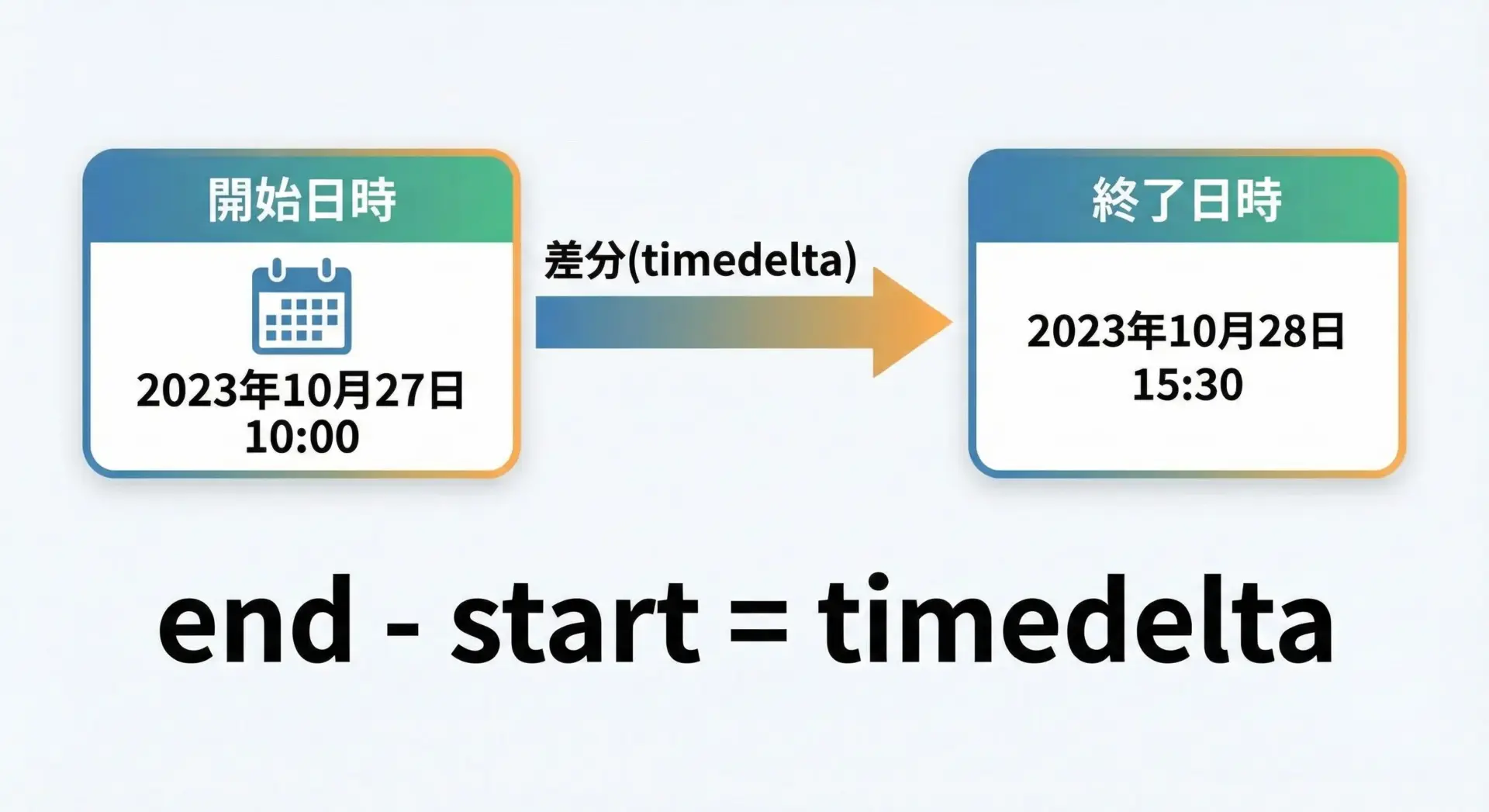
2つの日時の差分を求めるには、単純に引き算を行うだけです。
from datetime import datetime
start = datetime(2025, 4, 1, 9, 0, 0)
end = datetime(2025, 4, 3, 18, 30, 0)
diff = end - start
print("開始:", start)
print("終了:", end)
print("差分:", diff)
print("差分の型:", type(diff))開始: 2025-04-01 09:00:00
終了: 2025-04-03 18:30:00
差分: 2 days, 9:30:00
差分の型: <class 'datetime.timedelta'>datetime同士の差は必ずtimedeltaになります。
このtimedeltaから、必要な単位(日・時間・秒など)を取り出していきます。
日数差・時間差・秒数差を取り出す
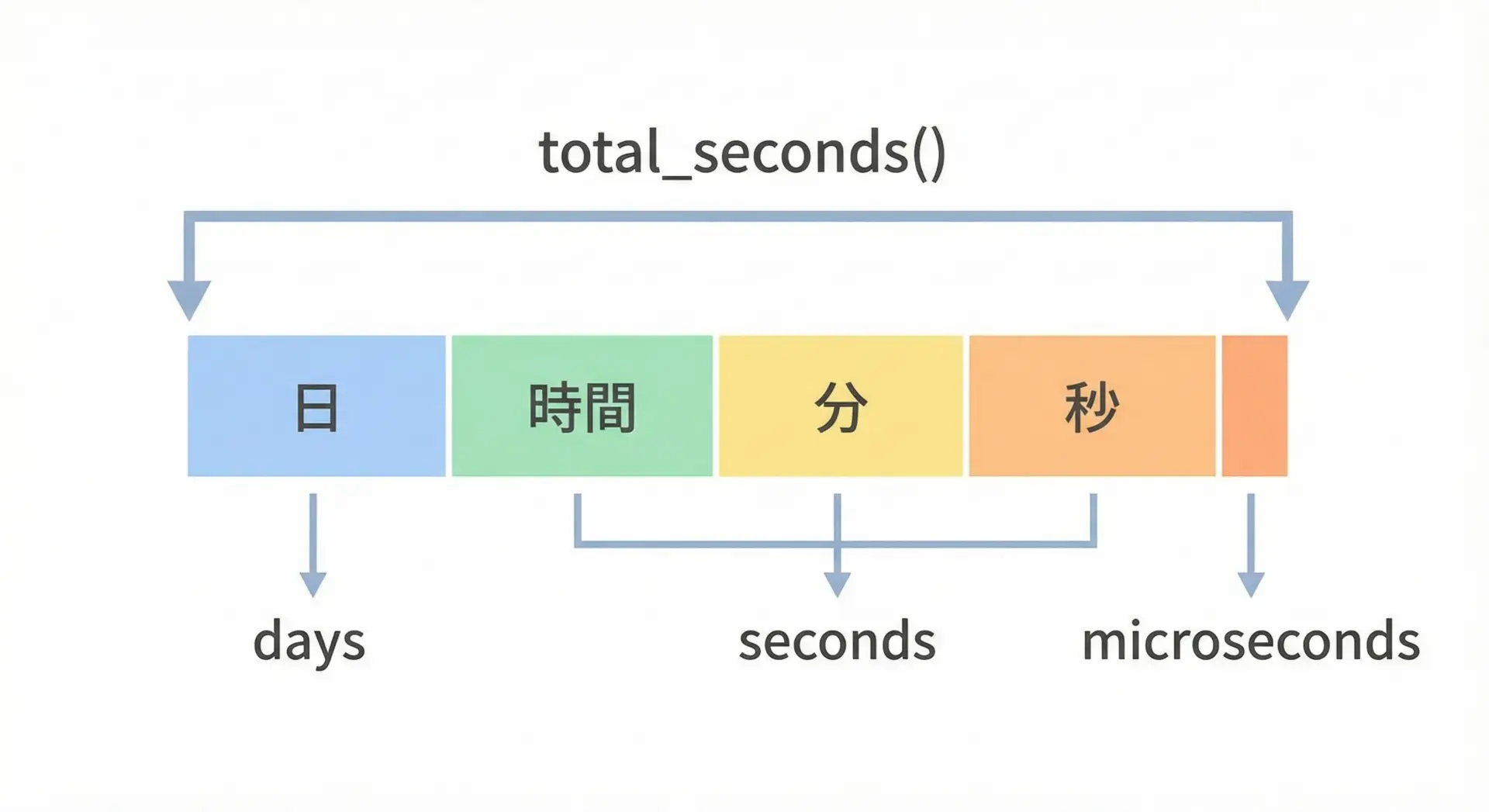
timedeltaには、主に次のようなプロパティやメソッドがあります。
days… 日数部分(整数)seconds… 1日未満の秒数部分(0〜86399)microseconds… 残りのマイクロ秒部分total_seconds()… 全体を秒数に換算した浮動小数点
from datetime import datetime
start = datetime(2025, 4, 1, 9, 0, 0)
end = datetime(2025, 4, 3, 18, 30, 0)
diff = end - start
print("差分:", diff)
print("日数部 diff.days:", diff.days)
print("1日未満の秒 diff.seconds:", diff.seconds)
print("マイクロ秒 diff.microseconds:", diff.microseconds)
print("合計秒 diff.total_seconds():", diff.total_seconds())
# 合計時間(時間単位)に変換
hours = diff.total_seconds() / 3600
print("合計時間(時間):", hours)差分: 2 days, 9:30:00
日数部 diff.days: 2
1日未満の秒 diff.seconds: 34200
マイクロ秒 diff.microseconds: 0
合計秒 diff.total_seconds(): 198600.0
合計時間(時間): 55.166666666666664「何日と何時間か」を分けて表示したい場合は、合計秒から手計算で分解します。
total_seconds = diff.total_seconds()
days = total_seconds // 86400 # 1日=86400秒
remain = total_seconds % 86400
hours = remain // 3600 # 1時間=3600秒
remain %= 3600
minutes = remain // 60 # 1分=60秒
seconds = remain % 60
print(f"{int(days)}日 {int(hours)}時間 {int(minutes)}分 {int(seconds)}秒")2日 9時間 30分 0秒日数・時間・分・秒のレポート形式がよく求められるため、このような分解ロジックを関数化しておくと便利です。
経過日数・経過時間のレポートを作成する

実務では、あるタスクやプロジェクトの経過時間を定期的にレポートすることがあります。
ここでは、開始日時と現在日時から、見やすいテキストレポートを作る例を紹介します。
from datetime import datetime
def format_timedelta_human_readable(delta):
"""timedeltaを「X日Y時間Z分」の文字列に整形する"""
total_seconds = int(delta.total_seconds())
sign = "-" if total_seconds < 0 else ""
total_seconds = abs(total_seconds)
days, rem = divmod(total_seconds, 86400)
hours, rem = divmod(rem, 3600)
minutes, seconds = divmod(rem, 60)
parts = []
if days:
parts.append(f"{days}日")
if hours:
parts.append(f"{hours}時間")
if minutes:
parts.append(f"{minutes}分")
if seconds or not parts:
parts.append(f"{seconds}秒")
return sign + "".join(parts)
project_start = datetime(2025, 1, 1, 9, 0, 0)
now = datetime(2025, 4, 1, 18, 0, 0)
elapsed = now - project_start
print("プロジェクト開始:", project_start)
print("現在:", now)
print("経過:", format_timedelta_human_readable(elapsed))プロジェクト開始: 2025-01-01 09:00:00
現在: 2025-04-01 18:00:00
経過: 90日9時間人間が読むレポートでは、単純な秒数ではなく読みやすい単位に分割することが重要です。
この関数は、遅延や残り時間の表示にもそのまま応用できます。
実務で使えるtimedeltaレシピ集
月次・週次レポート期間をtimedeltaで計算

BIレポートやバッチ処理では、「直近1週間」「先月1ヶ月分」などの集計期間をプログラムで計算する必要があります。
ここでもtimedeltaが役立ちます。
直近7日間の期間を求める
from datetime import date, timedelta
today = date(2025, 4, 10)
# 直近7日間(今日を含む)の開始日と終了日
days = 7
end_date = today
start_date = today - timedelta(days=days - 1)
print("直近7日間の開始日:", start_date)
print("直近7日間の終了日:", end_date)直近7日間の開始日: 2025-04-04
直近7日間の終了日: 2025-04-10週次レポート(月曜始まり〜日曜終わり)
from datetime import date, timedelta
def get_week_range(target: date):
"""指定日を含む週(月曜〜日曜)の開始日・終了日を返す"""
# weekday(): 月=0, ... 日=6
monday = target - timedelta(days=target.weekday())
sunday = monday + timedelta(days=6)
return monday, sunday
target = date(2025, 4, 10) # 木曜日と仮定
start_week, end_week = get_week_range(target)
print("対象日:", target)
print("週次開始(月):", start_week)
print("週次終了(日):", end_week)対象日: 2025-04-10
週次開始(月): 2025-04-07
週次終了(日): 2025-04-13月次レポート(1日〜末日)
from datetime import date
import calendar
def get_month_range(year: int, month: int):
"""指定年・月の月初日と月末日を返す"""
first = date(year, month, 1)
last_day = calendar.monthrange(year, month)[1]
last = date(year, month, last_day)
return first, last
start_month, end_month = get_month_range(2025, 4)
print("月初日:", start_month)
print("月末日:", end_month)月初日: 2025-04-01
月末日: 2025-04-30月の長さは28〜31日で変動するため、calendar.monthrangeと組み合わせて計算するのが安全です。
有効期限・締切日時をtimedeltaで管理
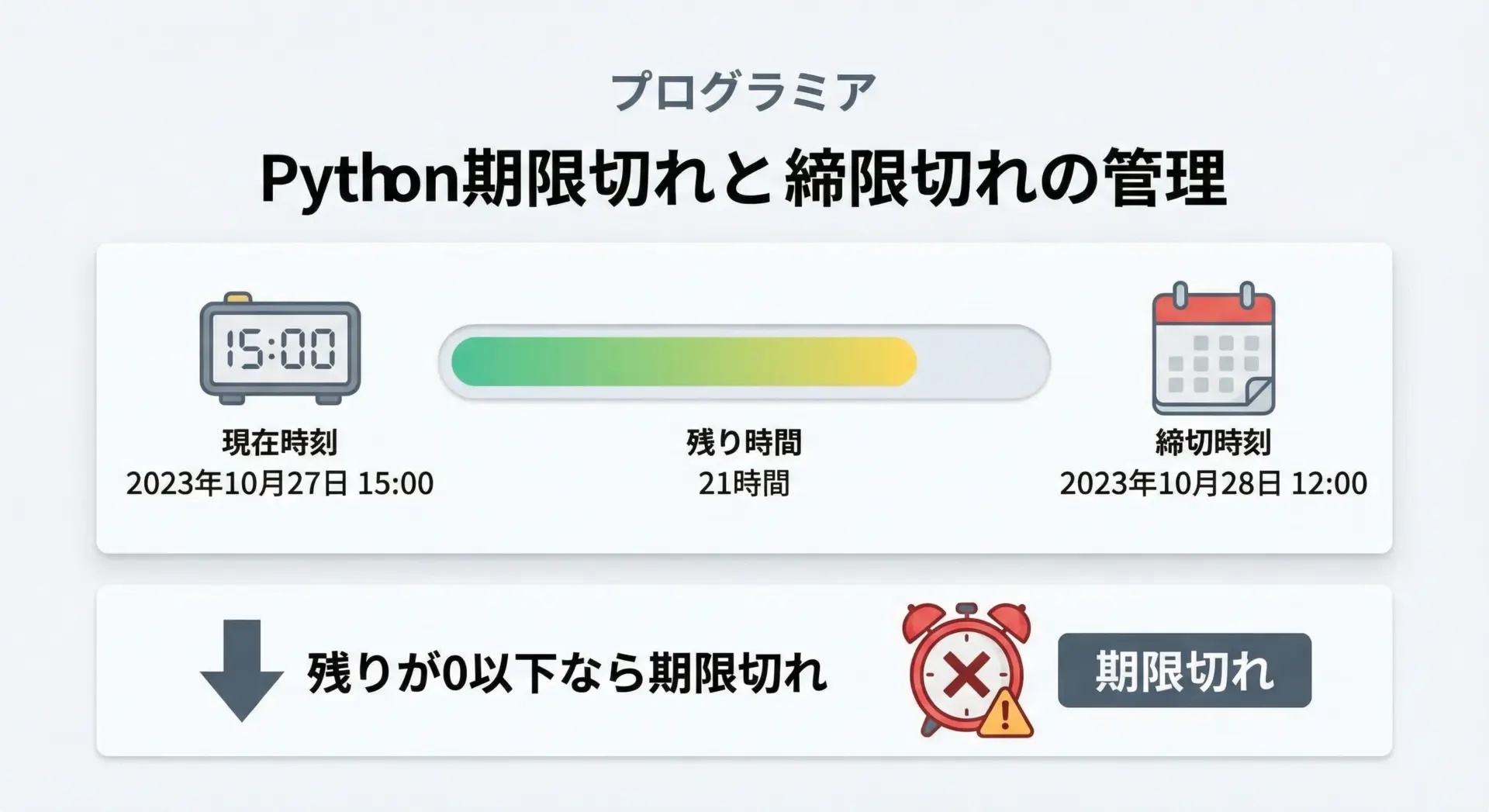
クーポンやトークン、申請締切など、有効期限の管理はほぼすべてのシステムで登場します。
timedeltaを使えば、現在時刻との差分でシンプルに判定できます。
from datetime import datetime, timedelta
def is_expired(issued_at: datetime, lifetime_hours: int, now: datetime) -> bool:
"""発行時刻から指定時間が経過しているかを判定"""
expires_at = issued_at + timedelta(hours=lifetime_hours)
return now >= expires_at
issued_at = datetime(2025, 4, 1, 10, 0, 0)
now = datetime(2025, 4, 1, 18, 0, 0)
expired = is_expired(issued_at, lifetime_hours=6, now=now)
print("発行時刻:", issued_at)
print("現在:", now)
print("有効期限切れか:", expired)発行時刻: 2025-04-01 10:00:00
現在: 2025-04-01 18:00:00
有効期限切れか: Trueより詳細な残り時間を表示することもあります。
def get_remaining_time(issued_at: datetime, lifetime_hours: int, now: datetime) -> timedelta:
expires_at = issued_at + timedelta(hours=lifetime_hours)
return expires_at - now
issued_at = datetime(2025, 4, 1, 10, 0, 0)
now = datetime(2025, 4, 1, 13, 30, 0)
remaining = get_remaining_time(issued_at, lifetime_hours=6, now=now)
print("残り時間(timedelta):", remaining)
print("残り時間(秒):", remaining.total_seconds())
print("残り時間(人間向け):", format_timedelta_human_readable(remaining))残り時間(timedelta): 2:30:00
残り時間(秒): 9000.0
残り時間(人間向け): 2時間30分「締切日時 = 基準日時 + timedelta」、「締切判定 = 現在日時と締切日時の比較」という形で統一しておくと、仕様変更にも対応しやすくなります。
ログやセンサー値の間隔チェックにtimedeltaを活用
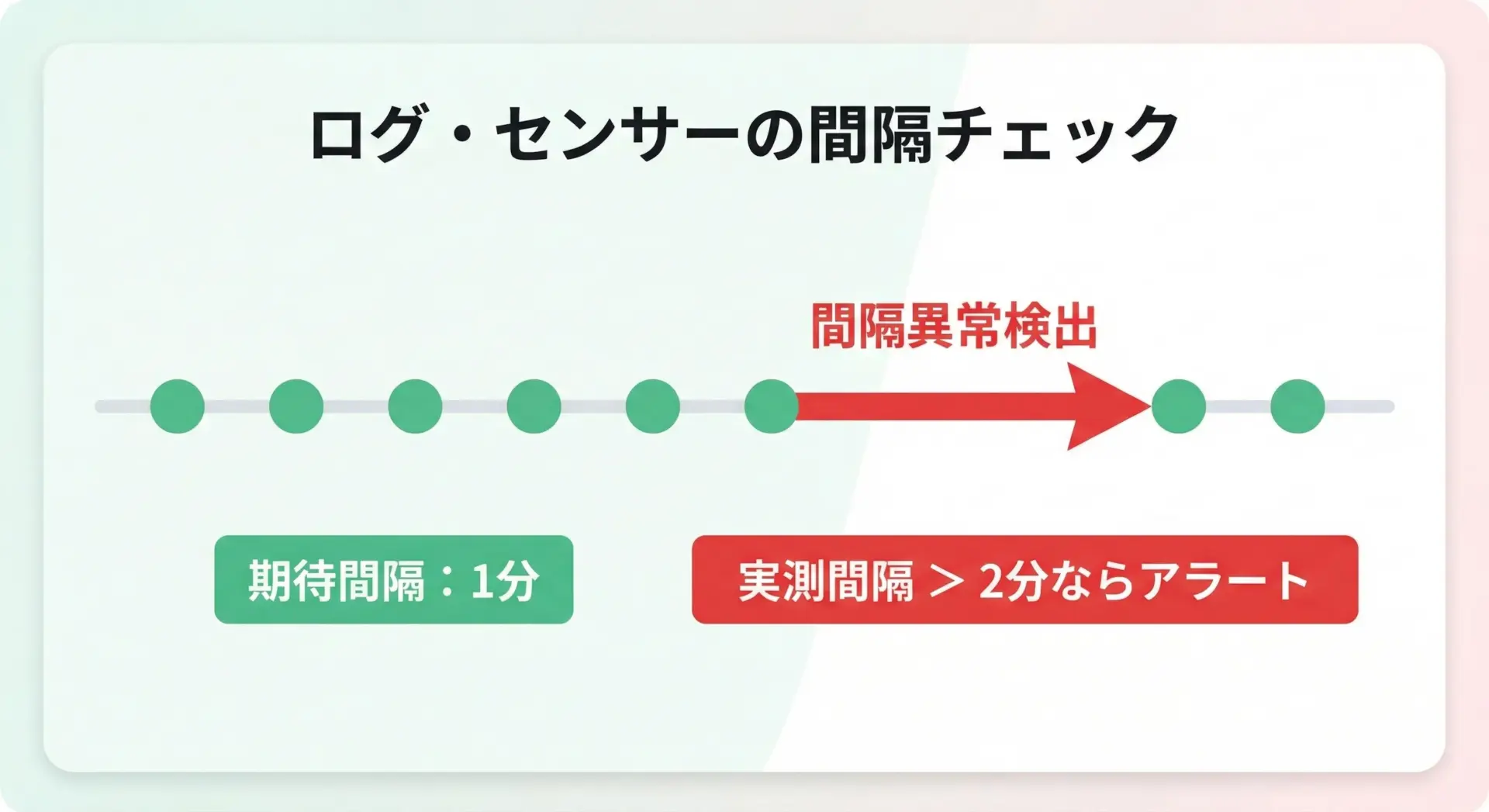
監視やIoTの現場では、ログやセンサー値が「想定どおりの頻度で届いているか」をチェックすることがよくあります。
このときも、timedeltaを使って直前のデータとの時間差を見ればよいです。
from datetime import datetime, timedelta
# ログのタイムスタンプ例
timestamps = [
datetime(2025, 4, 1, 10, 0, 0),
datetime(2025, 4, 1, 10, 1, 0),
datetime(2025, 4, 1, 10, 2, 5), # ここだけ少し遅い
datetime(2025, 4, 1, 10, 3, 0),
datetime(2025, 4, 1, 10, 6, 30), # ここは大きく遅延
]
EXPECTED_INTERVAL = timedelta(minutes=1)
ALERT_THRESHOLD = timedelta(minutes=2)
prev = None
for ts in timestamps:
if prev is not None:
interval = ts - prev
print(f"{prev} -> {ts} 間隔: {interval}")
if interval > ALERT_THRESHOLD:
print(" !! アラート: 間隔が長すぎます")
prev = ts2025-04-01 10:00:00 -> 2025-04-01 10:01:00 間隔: 0:01:00
2025-04-01 10:01:00 -> 2025-04-01 10:02:05 間隔: 0:01:05
2025-04-01 10:02:05 -> 2025-04-01 10:03:00 間隔: 0:00:55
2025-04-01 10:03:00 -> 2025-04-01 10:06:30 間隔: 0:03:30
!! アラート: 間隔が長すぎますここでは想定間隔(1分)よりも大きく離れた値(ALERT_THRESHOLD超え)を異常として検出しています。
さらに、平均間隔や最大間隔をレポートにまとめることもできます。
def analyze_intervals(timestamps):
intervals = []
prev = None
for ts in timestamps:
if prev is not None:
intervals.append(ts - prev)
prev = ts
if not intervals:
return None
total = sum((i for i in intervals), timedelta())
avg = total / len(intervals)
max_interval = max(intervals)
return {
"count": len(intervals),
"total": total,
"average": avg,
"max": max_interval,
}
result = analyze_intervals(timestamps)
print("測定数(間隔の数):", result["count"])
print("合計間隔:", result["total"])
print("平均間隔:", result["average"])
print("最大間隔:", result["max"])測定数(間隔の数): 4
合計間隔: 0:06:35
平均間隔: 0:01:38.750000
最大間隔: 0:03:30timedelta同士は足し算・割り算もできるため、このような統計的な処理にも自然に使うことができます。
まとめ
timedeltaは「期間」を表すクラスであり、datetimeと組み合わせることで日付・時刻の加算や差分計算をシンプルに記述できます。
日数・時間・分・秒レベルの計算だけでなく、営業日計算や締め日、有効期限、ログ間隔チェック、週次・月次レポート期間の算出など、実務で頻出するシナリオの多くをカバーできます。
日付や時間を扱う処理を書くときは、独自計算を行う前に「timedeltaで表現できないか」を一度検討すると、バグの少ないコードにつながります。

