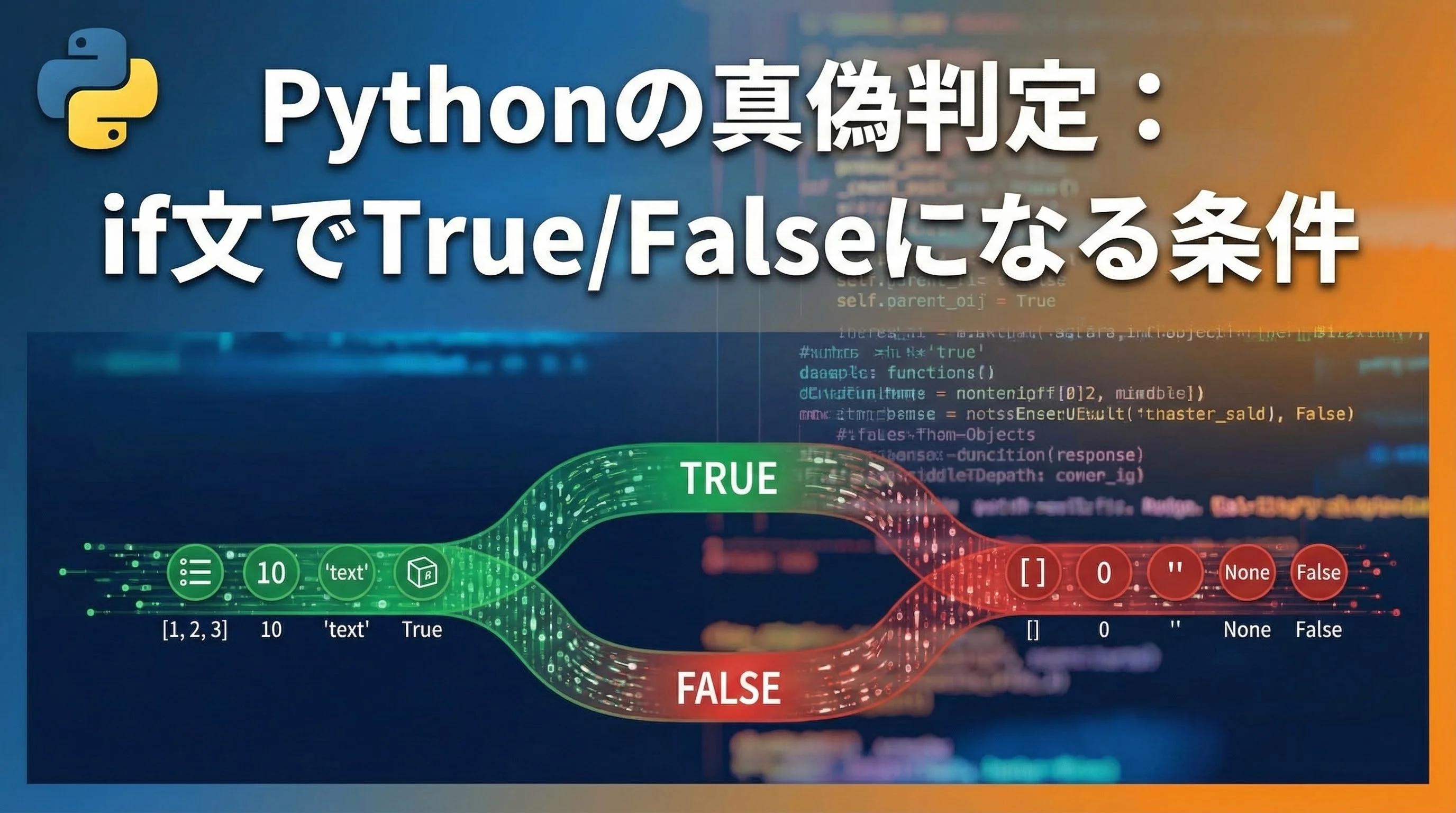Pythonではif文の条件式に必ずしもTrue/Falseそのものを書く必要はありません。
数値やリスト、文字列など、さまざまな値をそのまま書いても、自動的に「真」か「偽」かに解釈されます。
この仕組みを「Truthiness(真偽判定の規則)」と呼びます。
本記事では、Pythonがどのように値をTrue/Falseとみなしているのかを体系的に整理し、実践的な使い方と注意点まで詳しく解説します。
Pythonの真偽判定(Truthiness)とは
Truthinessとは何か
Truthinessとは、Pythonが値を条件式で評価するときに「真として扱うか」「偽として扱うか」を決めるためのルールのことです。
Pythonでは、if文やwhile文などの条件式に、次のようにさまざまな型の値を書くことができます。
if [1, 2, 3]:
print("リストはTrue扱い")このとき、if文のかっこ内ではbool([1, 2, 3])が内部的に呼び出され、その結果がTrueかFalseかで分岐が決まります。
つまり、条件式は必ず最終的にbool型のTrue/Falseに変換されてから評価されています。
真偽判定が行われる代表的な場面
Pythonでは、次のような場面でTruthinessが使われています。
- if文、elif文、while文の条件式
- and / or / not の論理演算
- 組み込み関数
any()やall()の評価 - 条件付き式
x if cond else yのcond部分
これらはいずれも「値 → boolに変換 → True/Falseで判定」という流れで動いています。
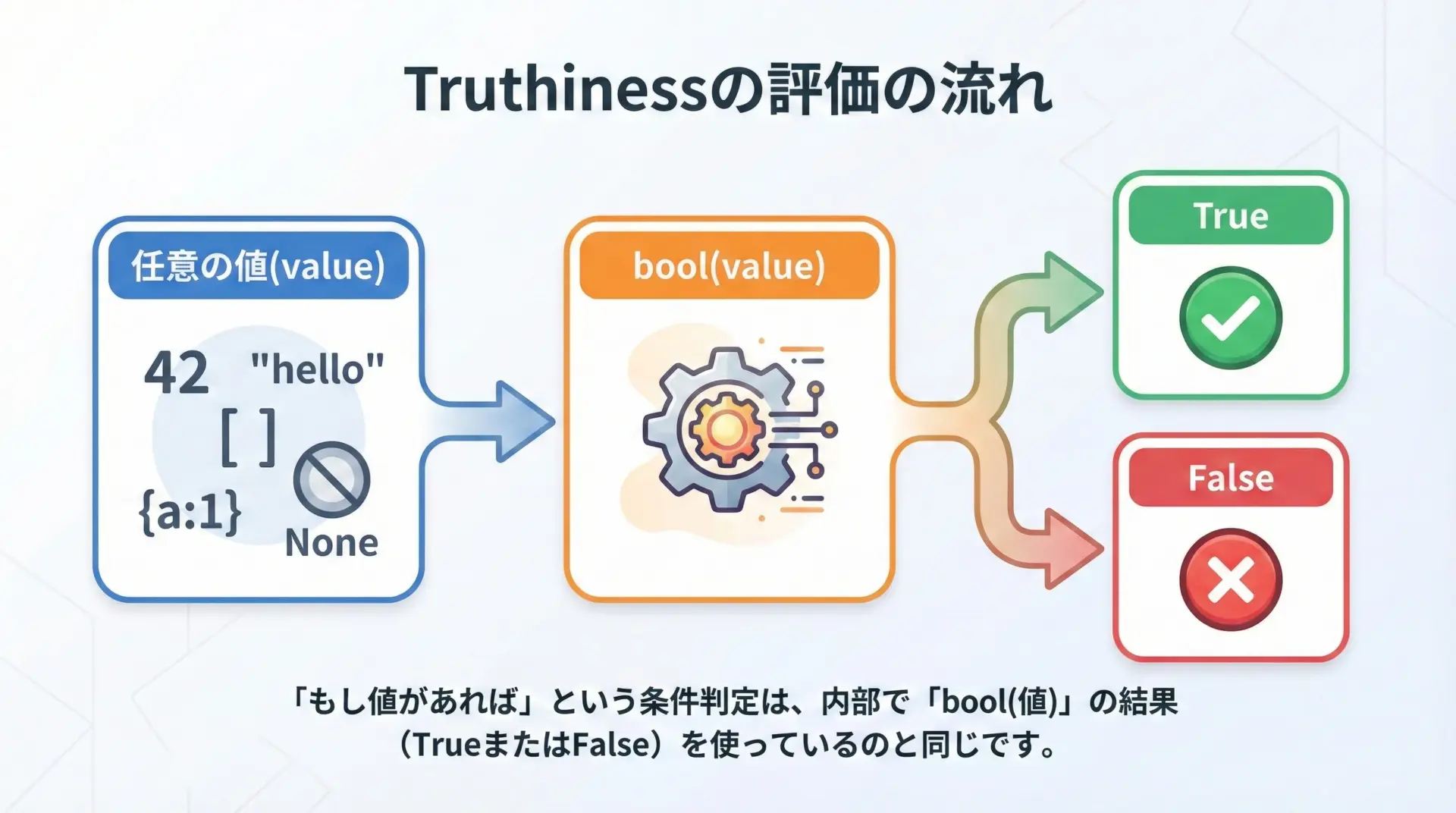
bool()関数とTruthinessの関係
Pythonにはbool()という組み込み関数があり、「この値はTrueなのかFalseなのか」を確認できます。
print(bool(1)) # 非ゼロの数値
print(bool(0)) # 0
print(bool("")) # 空文字
print(bool("abc")) # 非空文字列
print(bool([])) # 空リスト
print(bool([1, 2])) # 要素ありリストTrue
False
False
True
False
Trueこのbool()の結果が、そのままTruthinessの判定基準になっています。
真偽値bool型とその他の型の関係
Pythonには真偽値専用の型としてbool型があります。
代表的な値は次の2つです。
- True
- False
これらは実はint型のサブクラスであり、数値としても扱うことができます。
print(isinstance(True, bool))
print(isinstance(True, int))
print(True == 1, False == 0)
print(True + True, False + 5)True
True
True True
2 5このように、True/Falseは数値的には1/0と等価ですが、条件分岐では「論理的な意味」で使うことがほとんどです。
すべての値はboolに変換可能
Pythonでは、すべてのオブジェクトはboolに変換可能です。
組み込み型であれば、後述するルールに従い、TrueかFalseに決まります。
カスタムクラスであっても__bool__()や__len__()を定義することで、自分だけのTruthinessルールを持つことができます。
if文が評価しているのは「値」そのもの
if文の条件式は「TrueかFalseか」だけを見ているのではなく、「値をboolに変換した結果」を見ています。
つまり次の2つは同じ意味です。
value = [1, 2, 3]
# どちらも同じ意味
if value:
...
if bool(value):
...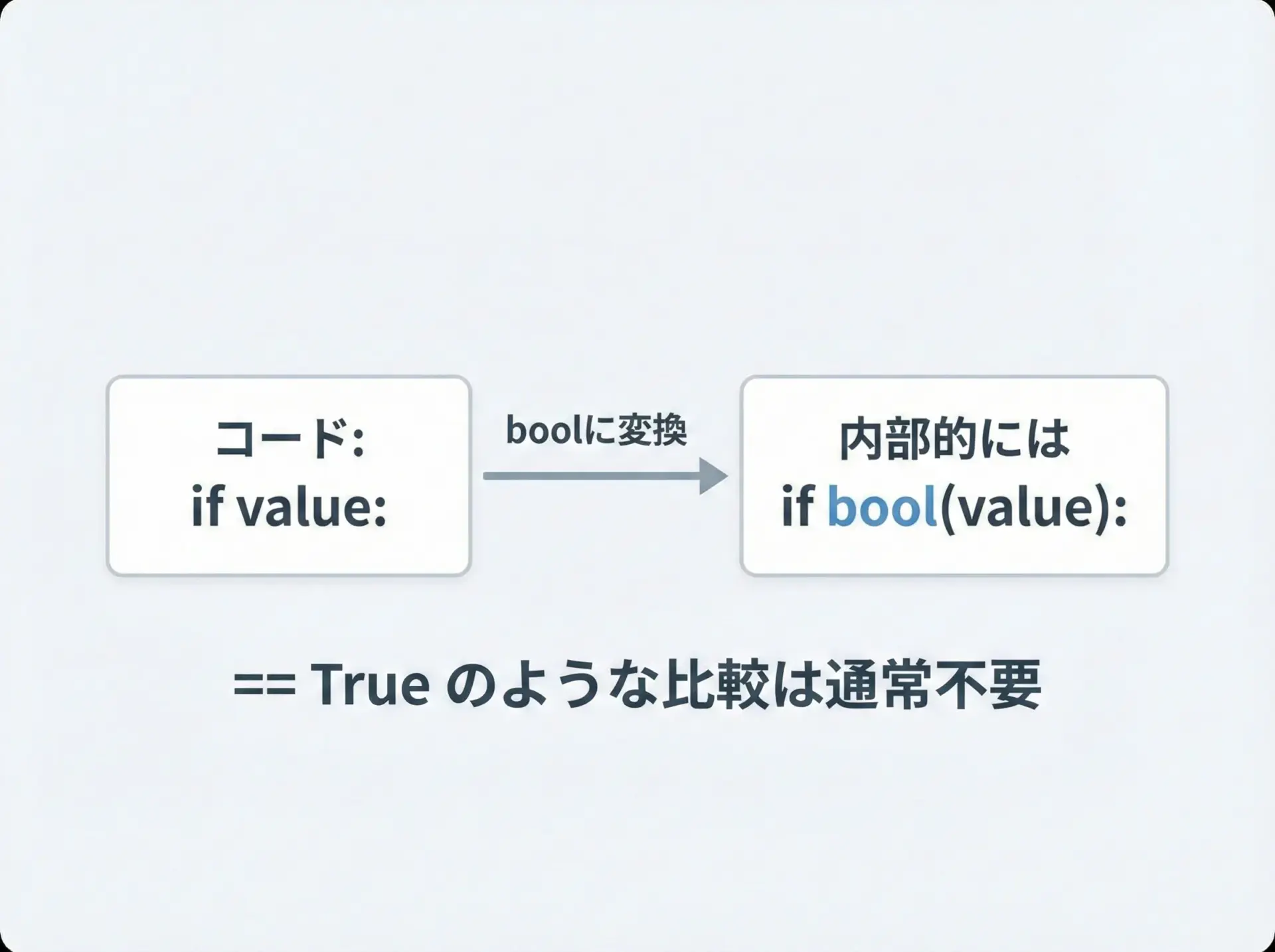
この仕組みを理解しておくと、わざわざ== Trueや!= 0のような冗長な書き方を避け、よりPythonicなコードを書けるようになります。
Trueと判定される値のパターン
Truthinessでは「False扱い」になる特別な値がいくつか決まっており、それ以外はすべてTrue扱いです。
まずは代表的な「Trueになるパターン」から見ていきます。
非ゼロの数値(int/float/complex)はTrue
数値型(int、float、complex)では、ゼロだけがFalse、それ以外はすべてTrueです。
numbers = [1, -1, 0.1, -3.5, 1+0j, 0+1j]
for n in numbers:
print(n, "=>", bool(n))1 => True
-1 => True
0.1 => True
-3.5 => True
(1+0j) => True
1j => Trueこれにより、たとえば次のようなコードが書けます。
balance = -100
if balance:
print("残高はちょうど0ではありません")数値を条件式にそのまま書くと、「0かどうか」の判定として使えるため、ループ回数の残りや、残高チェックなどで簡潔に書けます。
要素が1つ以上あるシーケンス(list/tuple/range)はTrue
リストやタプル、rangeなどのシーケンス型は、要素数が0ならFalse、1つ以上あればTrueになります。
print(bool([]), bool([1]))
print(bool(()), bool((1, 2)))
print(bool(range(0)), bool(range(1, 5)))False True
False True
False True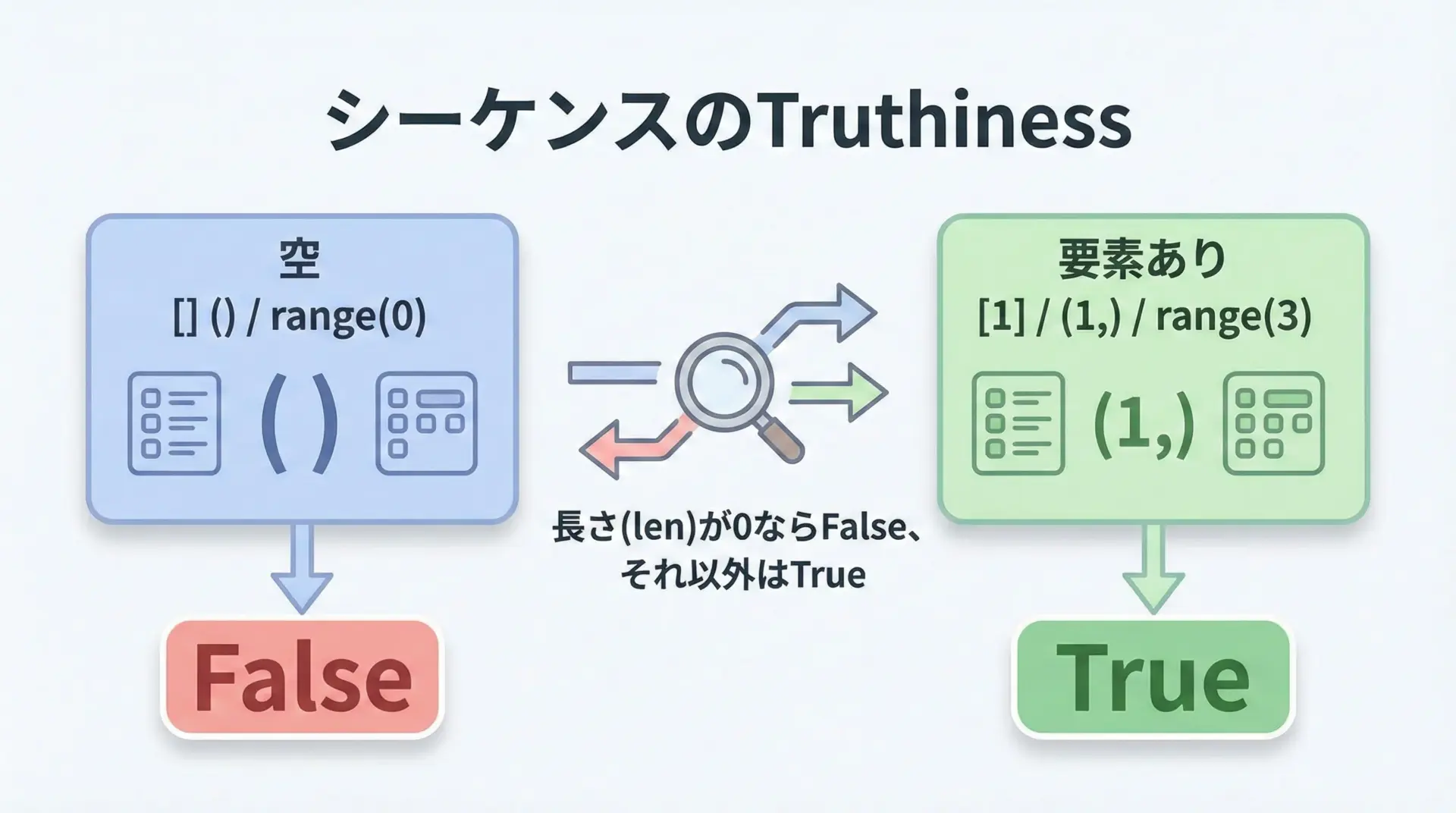
この性質により、次のような「空かどうか」のチェックが直感的に書けます。
items = []
if items:
print("要素があります")
else:
print("空のリストです")要素が1つ以上あるコレクション(dict/set)はTrue
辞書(dict)や集合(set、frozenset)など「要素を持つコレクション型」は、要素数が0ならFalse、1つ以上ならTrueです。
print(bool({}), bool({"a": 1})) # dict
print(bool(set()), bool({1, 2, 3})) # set
print(bool(frozenset()), bool(frozenset({1}))) # frozensetFalse True
False True
False True辞書の場合は「キーが1つ以上あるかどうか」の判定として使えます。
config = {}
if config:
print("設定値が読み込まれています")
else:
print("設定が空です")非空の文字列(str)はTrue
文字列もほかのシーケンスと同様、空文字""だけがFalse、それ以外はすべてTrueです。
print(bool("")) # 空文字
print(bool(" ")) # スペース1つ(空ではない)
print(bool("hello")) # 通常の文字列False
True
Trueここでよくある誤解は、スペースだけの文字列" "もTrueになるという点です。
長さが1以上あれば中身に関係なくTrueになるため、「空白だけ」であることを判定したい場合は別途.strip()などを組み合わせる必要があります。
s = " "
if s:
print("空文字ではありません") # ここは実行されるカスタムクラスのインスタンスがTrueになる条件
自前でクラスを定義した場合、そのインスタンスのTruthinessは次の優先順位で決まります。
__bool__(self)が定義されていれば、その戻り値(bool)で判定- 1がなければ、
__len__(self)が定義されていれば、長さが0ならFalse、それ以外はTrue - どちらもなければ、常にTrue
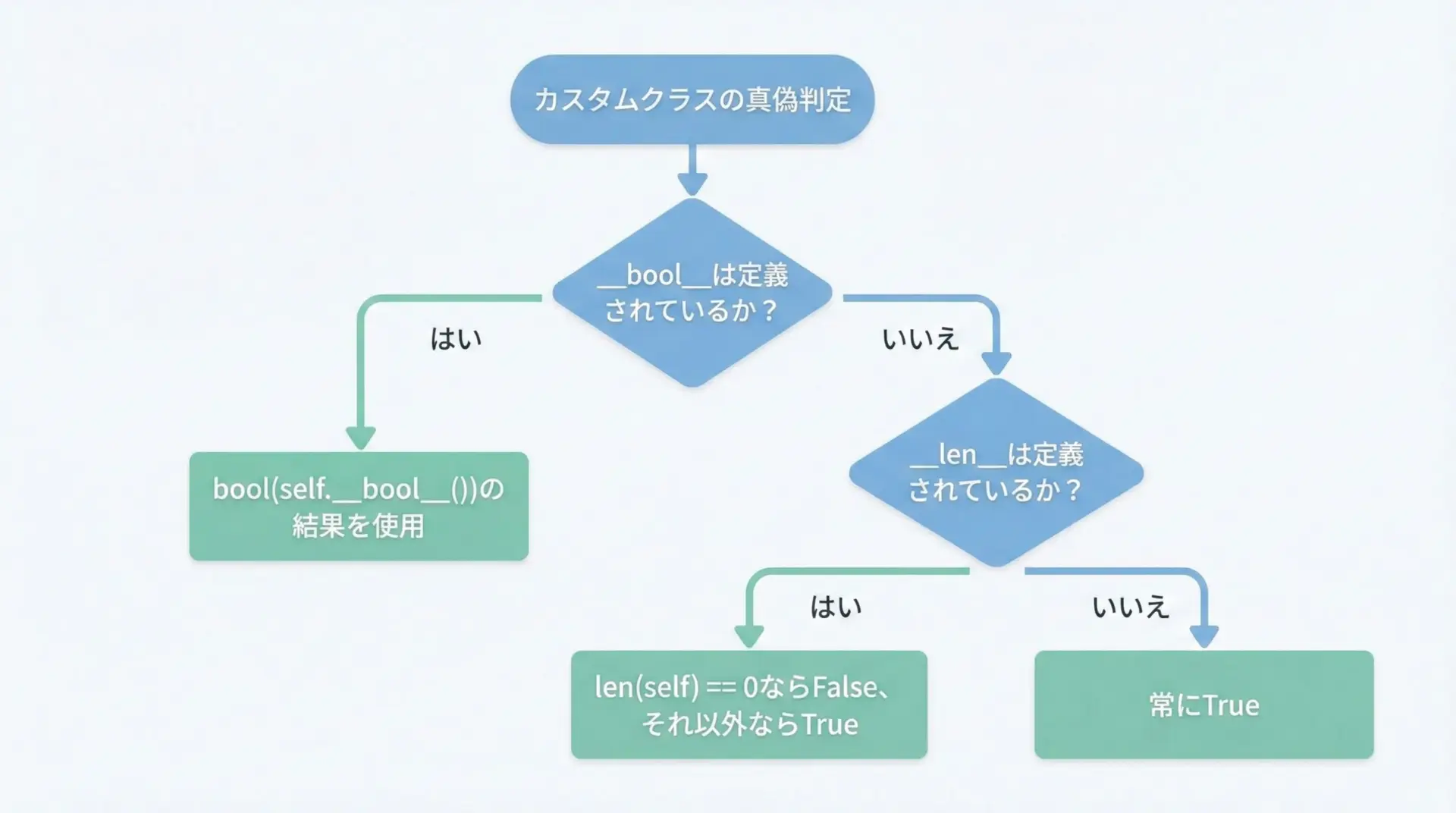
実際のコード例で確認してみます。
class Box:
def __init__(self, items=None):
self.items = items or []
def __len__(self):
# 要素数でTruthinessを決めたいので、lenを定義
return len(self.items)
class Flag:
def __init__(self, active):
self.active = active
def __bool__(self):
# activeの値をそのまま真偽値とする
return bool(self.active)
empty_box = Box()
box_with_items = Box(["apple"])
on_flag = Flag(True)
off_flag = Flag(False)
print(bool(empty_box), bool(box_with_items))
print(bool(on_flag), bool(off_flag))False True
True Falseこのように自分のクラスに直感的な「空かどうか」「有効かどうか」の意味づけを行い、そのままif文で使えるようにしておくと、利用者にとって扱いやすいAPIを設計できます。
Falseと判定される値のパターン一覧
ここからは、Pythonが特別にFalse扱いする値を一覧で整理します。
これを押さえておけば、それ以外はすべてTrueになります。
Falseそのもの
当然ながら、Falseというbool値はFalseと判定されます。
print(bool(False))FalseNoneは常にFalse
Noneは「値がない」ことを表す特別なシングルトンで、Truthinessでは常にFalseとして扱われます。
print(bool(None))Falseただし、NoneとFalseは同じものではありません。
値の意味が違うので、後述するようにis Noneを使い分けることが重要です。
数値の0(0, 0.0, 0j)はFalse
整数、浮動小数点、複素数の値が0であればFalse、それ以外はTrueです。
nums = [0, 0.0, 0j, -0.0]
for n in nums:
print(repr(n), "=>", bool(n))0 => False
0.0 => False
0j => False
-0.0 => FalsePythonでは-0.0も0として扱われるため、TruthinessでもFalseになります。
空のシーケンス(list/tuple/range)はFalse
前述のとおり、長さ0のシーケンスはFalseです。
具体的には次のようなものが該当します。
- 空リスト
[] - 空タプル
() - 空range
range(0)、range(5, 5)など
print(bool([]), bool(()), bool(range(0)))False False False空のコレクション(dict/set/frozenset)はFalse
辞書や集合系でも、要素数が0であればFalseです。
print(bool({}), bool(set()), bool(frozenset()))False False False空文字列(“”)はFalse
文字列では空文字""だけがFalseであり、長さ1以上の文字列はすべてTrueになります。
print(bool(""))Falseこの挙動は、「入力が空かどうか」をチェックしたい場面でよく利用されます。
user_input = ""
if not user_input:
print("入力が空です")__bool__や__len__でFalseになるオブジェクト
カスタムクラスの場合、__bool__()がFalseを返す、または__len__()が0を返すと、そのインスタンスはFalse扱いになります。
class AlwaysFalse:
def __bool__(self):
return False
class MaybeEmpty:
def __init__(self, count):
self.count = count
def __len__(self):
return self.count
af = AlwaysFalse()
empty = MaybeEmpty(0)
non_empty = MaybeEmpty(3)
print(bool(af))
print(bool(empty), bool(non_empty))False
False True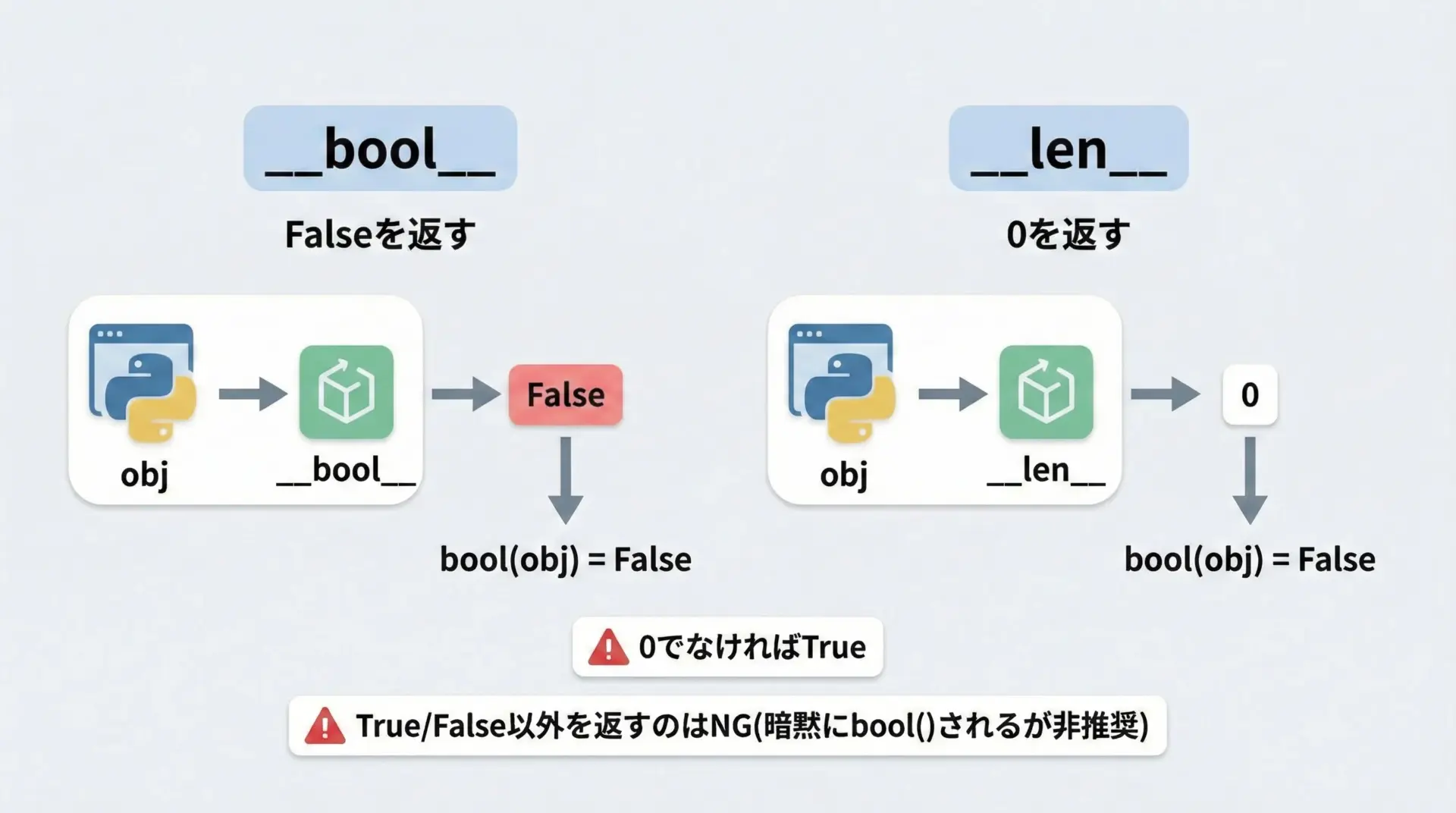
__bool__は必ずbool型(True/False)を返すべきであり、他の型を返すのは推奨されません。
また、__len__は整数を返す必要があります。
Pythonの真偽判定の実践例と注意点
ここまででTruthinessのルールを整理しました。
最後に、実際のコードでの使い方と、つまずきやすい注意点を解説します。
ifでよく使う真偽判定パターン
日常的なPythonコードでは、次のようなパターンがよく使われます。
シーケンスやコレクションが空かどうかの判定
「空かどうか」を知りたいとき、len()よりTruthinessを使うのがPythonicです。
items = []
# 推奨
if not items:
print("空です")
# これは冗長(ただし間違いではない)
if len(items) == 0:
print("空です")文字列入力の有無をチェック
ユーザー入力や設定値が「空でないか」をチェックする例です。
name = input("名前を入力してください: ").strip()
if name:
print("ようこそ,", name)
else:
print("名前が入力されませんでした")strip()で前後の空白を削除してからTruthiness判定をすると、「空白だけの入力」もきちんと空として扱えます。
設定値やオプションの有無を判定
辞書やNoneとの組み合わせで、オプション設定の有無を簡潔に判定できます。
config = {"timeout": 10}
timeout = config.get("timeout")
if timeout:
print("タイムアウト値:", timeout)
else:
print("タイムアウトは未設定または0です")ここでは0もFalse扱いになるので、「0なら未設定扱い」にしたい仕様であれば便利です。
一方で、「0も有効な値」としたいなら別の判定が必要になります(後述)。
「==」とTruthinessの違いに注意
Truthinessと比較演算(==, !=, < など)はまったく別のものです。
次のコードを比べてみます。
values = [0, 1, 2, "", "hi", [], [1]]
for v in values:
print(repr(v), "== 0 ?", v == 0, " bool(v) ?", bool(v))0 == 0 ? True bool(v) ? False
1 == 0 ? False bool(v) ? True
2 == 0 ? False bool(v) ? True
'' == 0 ? False bool(v) ? False
'hi' == 0 ? False bool(v) ? True
[] == 0 ? False bool(v) ? False
[1] == 0 ? False bool(v) ? True比較演算== 0は「値が0かどうか」だけを見ていますが、Truthiness(bool(v))は「型ごとのルールに従って真偽値を決める」動作になっています。
意図が「0かどうか」であれば==を使い、「空かどうか」「存在するかどうか」など論理的な有無であればTruthinessを使うというふうに、目的に応じて使い分けることが大切です。
is Noneで判定すべきケースと使い分け
Noneを判定したいときは、必ずis None / is not Noneを使うのがPythonの基本です。
なぜif value: ではダメなのか
次のような関数を考えてみます。
def find_index(lst, target):
try:
return lst.index(target)
except ValueError:
return None
idx = find_index([10, 20, 30], 10)
if idx:
print("見つかりました:", idx)
else:
print("見つかりませんでした")この場合、10はリストの先頭にあるためidx = 0になります。
しかし0はFalse扱いなので、「見つかりませんでした」と誤判定されてしまいます。
ここで意図しているのは「Noneかどうか」なので、次のように書くべきです。
if idx is not None:
print("見つかりました:", idx)
else:
print("見つかりませんでした")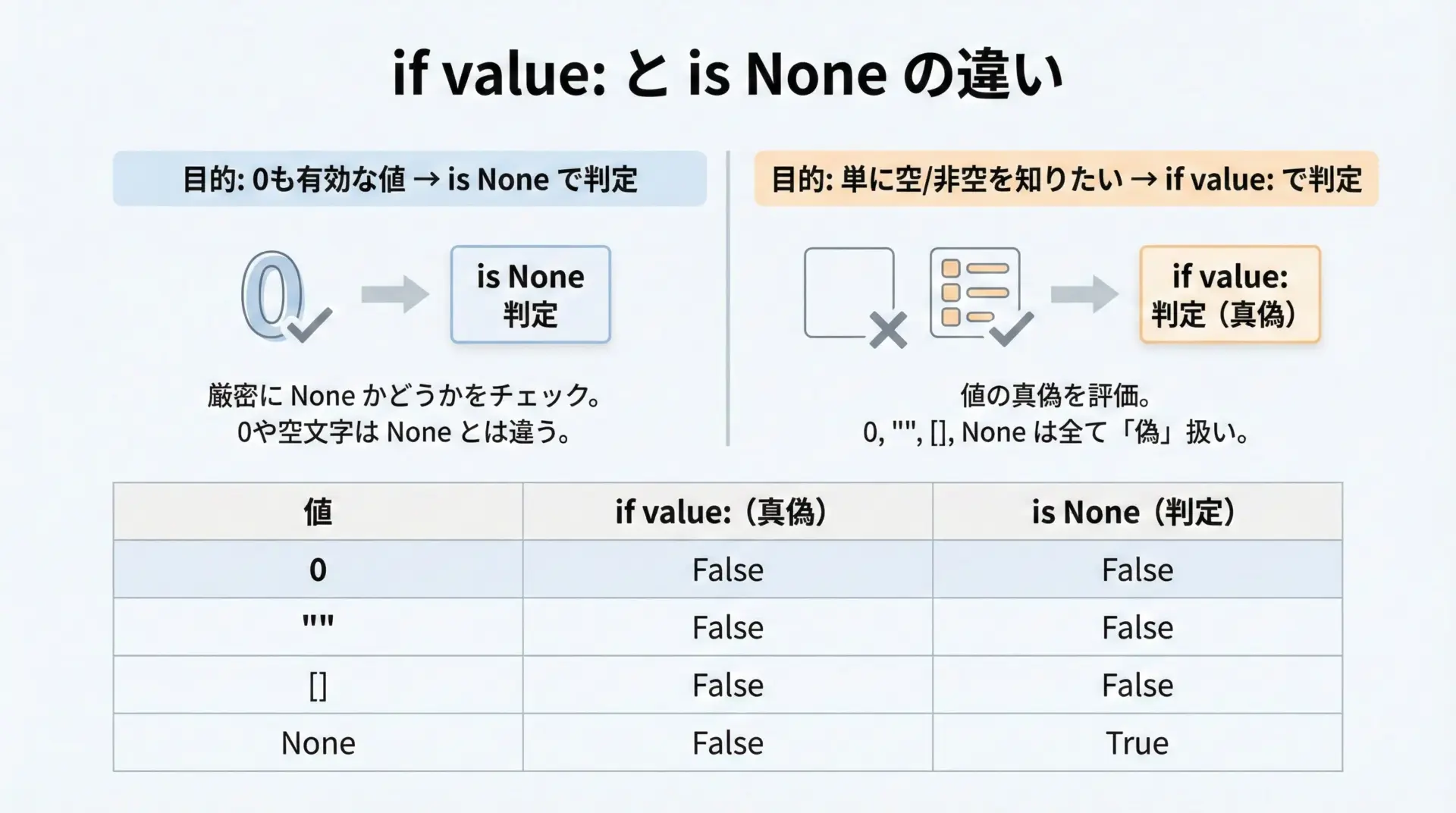
is / == の違い
==は「値が等しいか」isは「同じオブジェクトか(同一性)」
を判定します。
Noneは「ただひとつだけ存在する特別なオブジェクト」なので、同一性比較のisを使うのが慣習です。
x = None
print(x is None) # 推奨
print(x == None) # 動くが非推奨True
TrueTruthinessを活用したPythonicな書き方例
最後に、Truthinessをうまく活用した「Pythonらしい書き方」をいくつか紹介します。
デフォルト値の選択(or)
or演算子は左辺がTrueならそれを返し、Falseなら右辺を返します。
これを利用して、簡潔にデフォルト値を指定できます。
user_name = "" # たとえば入力値
display_name = user_name or "ゲスト"
print(display_name)ゲスト空文字はFalse扱いなので、空の場合は”ゲスト”が選ばれます。
入力チェックと処理を1行で
Truthinessと条件付き式を組み合わせて、次のような書き方も可能です。
data = [1, 2, 3]
message = "空です" if not data else f"要素数は {len(data)} です"
print(message)要素数は 3 ですコンテナの存在チェック
辞書で値を取得するとき、存在しないキーとNoneを区別したいかどうかによって書き方が変わります。
config = {"timeout": 0, "retries": 3}
# Noneなら未設定としてデフォルトを使う例
timeout = config.get("timeout")
timeout = timeout if timeout is not None else 30
print(timeout)
# 0もFalseなので、orだけだと意図しない挙動になる例
timeout2 = config.get("timeout") or 30
print(timeout2)0
30orを使うと、0や空文字も「未設定」とみなされてしまうため、「0や空文字も有効な値かどうか」で使い分ける必要があります。
カスタムクラスで直感的なif判定を実現
自分のクラスに__bool__や__len__を定義しておくと、次のように自然なif文が書けます。
class Stock:
def __init__(self, quantity):
self.quantity = quantity
def __bool__(self):
# 在庫が1以上ならTrue、0ならFalse
return self.quantity > 0
apple_stock = Stock(10)
banana_stock = Stock(0)
if apple_stock:
print("りんごは在庫があります")
if not banana_stock:
print("バナナは在庫切れです")りんごは在庫があります
バナナは在庫切れですこのようにドメインの意味に沿ったTruthinessを設計することで、読みやすく意図が伝わるコードを書くことができます。
まとめ
PythonのTruthinessは「False扱いになる少数の特別な値」と「それ以外はすべてTrue」というシンプルなルールで構成されています。
False扱いになるのは、False、None、数値の0、空のシーケンスやコレクション、空文字、そして__bool__や__len__がFalse/0を返すオブジェクトです。
これさえ押さえておけば、if文では値をそのまま書いて「空かどうか」「存在するかどうか」を自然に表現できます。
一方で、Noneを判定したいときはis Noneを使う、0も有効な値ならTruthinessに頼りすぎないなど、使い分けも重要です。
Truthinessの仕組みを理解しておくことで、よりPythonicで読みやすいコードを書けるようになります。